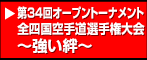|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||
 |
空手家として生きること~ある昇段審査の物語~ |
総本部およびWKO事務局長という重要な職務。その一方で、総本部師範代として道場指導も。空手、そして新極真会を、つねに多方面から見つめてきたのではないだろうか。3月1日に行なわれたJKO昇段審査会で、見事昇段を果たした小井泰三四段。その空手道とは、どのようなものなのか。 |
Text/空手LIFE・本島燈家 Photos:空手LIFE・米山祐子
|
 「おおりゃあ!」 強烈な上段蹴りを腕でブロックした直後、思わず叫びがもれた。相手に対して発したものではない。それは己への叱咤だった。 倒れるほどの痛みはない。耐えられないほどの苦しさでもない。それは当たり前のことと、最初から覚悟を決めていた。それよりも、この挑戦を認めてくれた師範たちに対して恥ずかしくないものを見せているだろうか---そんな思いが叫びとなった。 全力でやれているか。 気合いは入っているか。 礼はきちんとできているか。 自分はこの場に値する人間か。 10人組手は、6人目を迎えていた。すでに突きや蹴りを全身に浴び、呼吸もやや荒くなっていたが、頭の中ではつねに客観的に自分自身の姿を観察していた。 4年ぶりの昇段審査には、さまざまな思いがあった。40歳という節目の年齢に達したこともある。総本部師範代として埼玉中央道場での指導をはじめたことで、今まで以上に率先して範を示さなければいけないという使命感も生まれていた。だからこそ、一瞬も妥協したくなかった。 ふつうなら疲労とダメージで失速してしまいがちな10人組手の後半。しかし、その動きはおとろえるどころか、時間の経過とともに活力がみなぎっていくようだった。7人目にして優勢勝ちを収めると、8人目も気合いとともに積極的に前進していった。 審査委員長の緑健児代表が声をかける。緑代表は、人生で大きな影響を受けた人物のひとりだ。とくに2008年は海外の大会や指導に同行する機会が多く、魂で引っ張っていくような迫力やリーダーシップに感銘を受けた。 そして、もうひとり。その挑戦を特別な目で見つめる人物がいた。三好一男師範である。はるばる高知からやってきたのは、組手の主審を務めながら、弟子を一番近くで激励するためだった。実際、繰り広げられる攻防に向けられた厳しいまなざし、握りしめられた拳には、言葉ではないエールが入り混じっているように見えた。 |
礎を築いた学生時代小井泰三は、1968年12月22日、徳島県に生まれた。少年時代、世はちょっとしたカンフーブームだった。リー・リンチェイ(ジェット・リー)のように本格的な中国武術を駆使する映画スターも、日本でメジャーな存在となっていた。「ケンカに強くなりたい」。男なら一度は抱くそんな思いは、当初は拳法へと向けられた。中学に入ると少林拳の通信教材で技を学びながら、友人たちと“ケンカクラブ”なるものを作り、近所の神社でボクシンググローブをつけて殴り合っていた。 強さを求める心は、中学3年の時にフルコンタクト空手と巡り合う。地元の道場で稽古するうちに極真空手の存在を知り、高知大学進学と同時に入門。それが三好道場だった。さらに大学の極真同好会にも入会し、並行して稽古を重ねた。同好会では、のちに第四代目の主将を務めることとなる。 師範の教えもあったからか、文武両道は小井の重要なテーマだった。それは大学時代だけで終わらず、上場企業に就職するとともに上京し、城南支部に籍を置いてからも変わらなかった。それも、ただこなすだけではない。仕事も120%、空手も120%という理想を追求した。どんなに忙しくても、夜中の帰宅が続いても、稽古の時間だけは確保した。 選手を引退したのは30歳。日の丸を背負うことはなかったが、地方大会から着実に経験を積んだ小井は、第11回ウエイト制で3位入賞を果たしている。“世界”の舞台は、手の届く距離にあった。 |
 |
 |
 |
 |
 |
二つの転機転機は、2001年に訪れた。父が他界したため、兄とともに家業に打ち込んでいた時だ。肝炎と肺炎を併発して入院。さらに疲労やストレスが蓄積されたせいか、十分な呼吸ができなくなってしまう。靴ひもを結ぶために身をかがめたり、風呂の水圧を受けただけでも苦しくなる。病院をハシゴしても、明確な答えは出ない。苦悩の日々が長く続いた。 横隔膜が動いていないという原因が判明するまで、かなりの時間がかかった。その後、ペットボトルの空気を吸い込むトレーニングなどを続け、さいわい症状は徐々に回復へ向かう。あらためて人生というものを考える機会だった。 総本部事務局に入ったのは、同じ年のことだ。以前より話はあったが、大恩ある三好師範と緑代表から本格的に誘われ、決意した。 事務局長としての多忙な日々がスタートした。大会をはじめとする催しでは裏方として東奔西走。また、何か問題が起こった時、小井が真っ先に現場にかけつけて状況改善に努めたことは、関係者なら誰もが知っているだろう。まさに、縁の下の力持ちである。 この間も稽古は休まなかった。組手やミットはできなくても、限られた時間でランニングやスクワット、四肢など、とくに下半身の維持をはかった。そして、2005年に参段への昇段を果たす。 最近は高野優希や山本将也が新たに事務局入りしたため、始業前に一緒に汗を流すこともある。どんな状況でも、できることを全力でやる。その信念を持ち続けたからだろう。今回の審査に対しても、稽古不足という不安はなかった。 |
 |
 |
 |
道に終わりなし基本、型、体力審査、組手と、審査は進んでいく。小井は、ひたすら自問自答を続けた。 おまえは全力でやれているか。 気合いは入っているか。 組手9人目の相手は高野。10人目は城南支部の仲間だった佐伯健徳。現役トップクラスの強烈な攻撃を受けながら、小井は真っ向から立ち向かった。 10人組手を完遂すると、道場に響きわたる声で「押忍、ありがとうございました!」と十字を切った。今回できなかったと感じたことは、今後の課題になる。次の目標が見えたことはありがたい。そう小井はいう。では、試合という舞台をはなれた今、これからどんな道を歩んでいくのだろうか。 昇段審査に関して、小井には忘れられない思い出がある。それは初めて黒帯を巻いた1990年のこと。高知支部では首都圏に負けない空手家を育てるため、15人組手という厳しいハードルを課していた。それを乗り越えて昇段したとき、三好師範が自分の手で黒帯を締め、手を上げてくれたのだ。 それから19年の歳月が流れた。四段になった弟子が、師のもとへ歩み寄る。わが子を見るような目で、師はその肩をポンとやさしく叩いた。 |
 高知の三好道場本部には、思い出の場面が今も数多く飾られている。 |